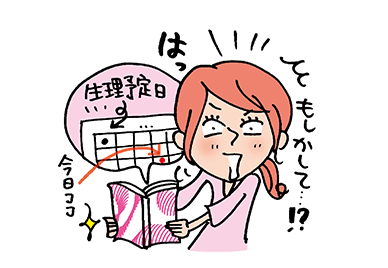チーコさんの長男、テルテルは生後2~3カ月の頃から指しゃぶりをしていました。それをみたチーコさんが試しに泣き止まない時におしゃぶりをくわえさせたところ、ピタッとなきやんだそうです。
それ以来、おしゃぶりは、外出先でぐずったり、夜の寝かしつけに手こずった時の「救世主」に!
でも、テルテルが成長して歯が生えた頃に「ずっとおしゃぶりをしていたら出っ歯になるのでは?」と、チーコさんは不安になり、断乳ならぬ「断おしゃぶり」を決行したそうです。
チーコさんが心配した「おしゃぶりをし続けると歯並びに影響が出るらしい」という噂、よく耳にするのですが、本当に歯並びに影響がでるのでしょうか。そのウワサの真偽と、子どもの歯並びが悪くなると将来的にどんな影響が出るのかなどを、小児歯科医専門医で東京都内に4つのクリニックを持つキッズデンタル代表の坂部潤先生に教えていただきました。
Q:おしゃぶりをしていると歯並びに影響を与えますか。
A:全く歯並びに影響しないわけではないが、3歳までならOKです。
おしゃぶりをしていると、歯並びに影響が出ることがあります。ただ赤ちゃんにとって、おしゃぶりは「精神安定剤」としての役割もあるので、3歳までのおしゃぶりならOKと考えてください。
また3歳までの時期は、歯並びや、歯並びに影響するあごの状態も成長の途中段階であるため、一時的に上あごが前に出る、いわゆる「出っ歯」のような状態になることがあります。でも、ほとんどが自然に治るので過度に心配しなくて大丈夫でしょう。
ただし3歳を過ぎると少しずつあごの状態も歯並びも固定されてくるため、自然治癒するのは難しくなってきてきます。
Q:歯並びが悪くなると、見ためがよくない他にどのような影響を与えますか。
A:口呼吸になる、決まった歯を酷使する、発音が不明瞭になる、姿勢が悪くなりやすいなど、将来にわたっていろいろな影響が出やすくなります。
歯並びが悪くなるとさまざまな影響が出ると考えられていますが、主にどんな影響が生じやすくなるのかを解説します。
1:かみ合わせが悪くなり、一部の歯に負荷がかかる
本来ならどの歯も均等に働いている状態が理想です。ただ歯並びが悪くなると、上下の歯のかみ合わせも悪くなり、ほとんど働かない歯と、常に働かざるを得ない歯が出てきます。常に働かざるを得ない歯には負荷がかかりやすくなり、将来いたみやすくなってしまいます。
2:口呼吸になり、虫歯や歯周病、感染症にかかりやすくなる
通常、私たちは口を閉じて鼻で呼吸をしています。口を閉じるために、無意識に舌を正しい位置(上あごに舌がはりついた状態)に置いています。
歯並びが悪くなると上あごが狭くなるため、舌を正しい位置に置けなくなり、口で呼吸をすることになります。
唾液には抗菌成分が含まれていて、外からのウイルスが体内に入ることをブロックする役割を担っていますが、口呼吸になると唾液が渇いて抗菌成分もなくなってしまうので、虫歯や歯周病、インフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。
3:猫背になりやすい
歯並びが悪いと口呼吸になりやすいことは上記で解説しましたが、口呼吸になると、あごを前に突き出すような姿勢になることが多いので、猫背になりやすくなります。(但し猫背の人、全員が歯並びが悪いわけではありません)
このほか、発音が不明瞭になるなど、歯並びが悪いと、赤ちゃんの将来にわたってさまざまな不具合が報じる可能性が高くなります。そのため、3歳を過ぎたらおしゃぶりを卒業した方がいいでしょう。
Q:おしゃぶりの形状によって歯ならびに影響の出やすいおしゃぶり、出にくいおしゃぶりというのはあるのでしょうか。
A:舌の動きを正しくさせるおしゃぶりなら、歯並びをととのえる効果あり。
今はさまざまなメーカーからいろいろなおしゃぶりが出ていますよね。なかには舌の動きを正しくし、歯並びをととのえる効果があるものも販売されています。
遺伝や生まれつき舌の動きが正しくない場合は、このようなおしゃぶりをおすすめし、舌の動きが正しくなるよう使ってもらうことがあります。
また、一般的に素材が硬いおしゃぶりは、歯並びに良くない影響が出やすいため、できるだけやわらかい素材のものの方がいいでしょう。
Q:おしゃぶりと同様、指しゃぶりも歯並びに影響が出やすいのでしょうか。
A:影響が出る可能性あり。こちらも3歳までならOKと考えて。
指しゃぶりもおしゃぶりと同じく歯並びに影響が出る可能性がありますが、3歳までならOKと考えてください。
Q:投稿者の長男、テルテルくんのように自らおしゃぶりを卒業できればいいですが、なかなかうまくいかないケースも多々あります。うまくやめさせる方法をお教えください。
A:歯並びにまだ影響が無い場合は言葉で伝える、なめると苦い味がする無害のマニキュアをつけるなどの方法で「断おしゃぶり」を。
歯並びに影響が無い場合は、どうしてやめなければいけないのかなどをママやパパがお子さまに説明してあげてください。3歳を過ぎると、こちらが話したことが通じるようになるので、すんなり納得する場合もあります。
指しゃぶりにのみ使える方法ですが、子どもが大好きなキャラクターの絆創膏をしゃぶる指に貼り、「〇〇(キャラクターの名前)がはがれちゃうから舐めるのをやめようね」などと声がけしてみるのもいいでしょう。
また、おしゃぶりや指に、なめると苦く感じる無害のマニキュアを塗るのも方法の1つです。
「断おしゃぶり」をする際、あまりプレッシャーをかけすぎないよう注意してください。おしゃぶりや指しゃぶりをやめても、「常に髪の毛をさわってしまう」など、新たなクセに移行するだけになってしまうこともあります。
無理をせず、子どものペースや表情を見ながら進めることが大切です
Q:すでに歯並びで気になるところがある場合は、どうすればいいでしょうか。
A:小児歯科専門医、または小児をよく診察している先生に相談を。
すでに上の歯が前に出ている、下あごが常に前に出ている、口で呼吸をしているなど、気になることがある時は、歯科医院での治療や、専用の器具で矯正が必要となるケースがあります。
一度小児歯科専門医、または子どもをよく診察している歯科医にぜひ相談してみてくださいね。
ゼクシィBaby WEB MAGAZINEの記事

歯学博士(小児歯科学)
坂部 潤先生(キッズデンタル代表/医療法人スマイルベア理事)
大学病院での小児歯科専門医療の実践や、米国UCLA小児矯正科への留学経験を経て、小児歯科、小児矯正歯科専門医院の「キッズデンタル」の代表に就任。4児の父親としての経験を生かし、ママやパパ、子どもたちに健康な歯でいるためのアドバイスをわかりやすく行っている。
日本大学歯学部兼任講師(小児歯科学)。日本小児歯科学会認定小児歯科専門医。日本歯科矯正学会会員。元UCLA小児矯正歯科客員研究員。
※プロフィール情報は記事掲載時点の情報です。